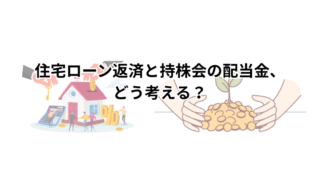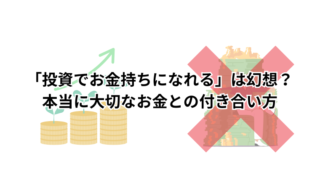【民間保険、ほとんどの人にいらない理由】お金に困らない人生を送るために知っておくべきこと
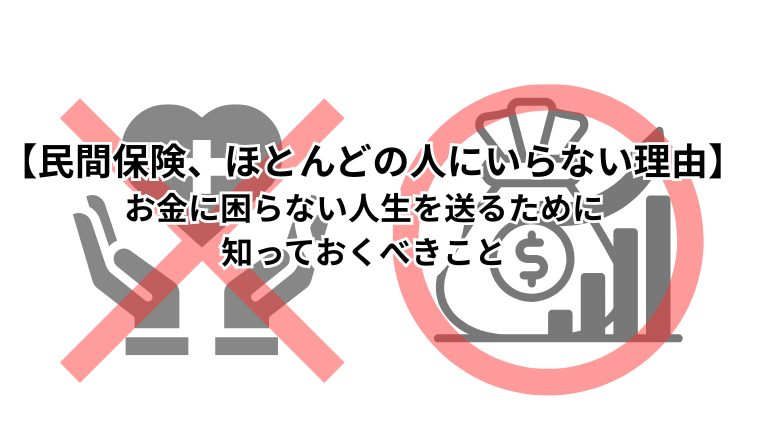
【民間保険、ほとんどの人にいらない理由】お金に困らない人生を送るために知っておくべきこと

こんにちは。40歳でリタイアした鼻つぶれぱぐ男です。
このブログでは、金融機関や周囲の人がなかなか教えてくれない、お金に関する身近でリアルな話をお届けしています。
今回は「民間保険はほとんどの人にいらない」というテーマでお話ししていきます。
新年度が始まり、新しい環境で生活をスタートする方も多いと思います。
そんな節目だからこそ、お金に関する大切な考え方を改めてお伝えしたいと思います。
保険の基本「ほとんどの人に民間保険はいらない」
保険と一言で言っても、生命保険・医療保険・学資保険・ペット保険などさまざまです。
しかし、結論から言うと「ほとんどの人にとって、民間保険は不要」です。
民間保険は不安を煽るプロである営業マンによって勧められます。
ですが、その不安に流されて契約するのは大変危険です。
まずは「なぜいらないのか?」という理由をしっかり見ていきましょう。
【1】貯蓄型保険がいらない理由
例えば養老保険や学資保険、解約返戻金付きの終身保険などの貯蓄型保険。
これらは「お金を貯めること」が目的です。
しかし、保険会社は預かった保険料を運用して利益を出し、そこから人件費や利益を差し引いたうえで、わずかな利回りを私たちに返してくれるだけです。
だったら、自分で投資信託や債券を買った方が、ずっと効率よくお金を増やせます。
特に今はネット証券などで誰でも簡単に資産運用ができる時代です。
ドル建ての終身保険なども、実際は米国債などで運用しているのに、返ってくる利回りは1%以下なんてことも。
「だったら最初から自分で米国債を買えばいいのでは?」というのが、正直なところです。
【2】医療保険も基本的にいらない
医療保険に入っている人も多いですが、特に日本人であれば「健康保険」という最強の保障制度にすでに入っています。
・通院:1~3割負担(年齢による)
・入院:高額療養費制度で上限あり(所得に応じて月10~20万円程度)
・差額ベッド代や食事代なども含めても、1か月の入院で30万円以上かかることは稀
これらを考えると、医療保険で備える必要はあまりありません。
毎月の保険料を貯金や資産運用に回した方が、長期的に見て合理的です。
【3】それでも保険が必要なケースとは?
すべての人が完全に保険不要かというと、そうではありません。
以下のような場合は、最低限の保険加入を検討しても良いかもしれません。
●家族の生活を支えている人
もし自分が亡くなった場合に、家族の生活が立ち行かなくなる場合、定期死亡保険(掛け捨て)に入るのはアリです。
ただし、以下を確認しましょう。
- 死亡退職金はあるか?
- 遺族年金はどれくらい出るか?
- 家計の必要生活費は月いくらか?
これらを把握した上で、最低限の保障額だけにするのがポイントです。
●現金で医療費を払えない人
万が一の入院で、10万円~30万円の支払いができないという方は、医療保険に入るのも選択肢です。
ただし、その場合も「県民共済」などの割戻金がある共済保険のような、コストパフォーマンスの良い保険を選びましょう。
【4】新生活で保険の勧誘を受けたときの対処法
新社会人や転勤者など、新しい環境に入ると保険の勧誘が増えることがあります。「会社の福利厚生の一環」として、説明会で民間保険を勧められることもあります。
そんなときは、以下のように切り返してください。
- 「もう入っているので大丈夫です」
- 「専門家に相談してから決めます」
- 「こちらから連絡します」
無理に断る必要はありませんが、余計な保険に入らないためには「距離を取る」ことが重要です。
まとめ:保険は”不安”ではなく”合理性”で選びましょう
民間保険は、ほとんどの人にとって必要ありません。
不安を煽るセールストークに惑わされず、自分の状況と制度を正しく理解したうえで、必要な保障だけを見極めましょう。
健康保険や遺族年金などの公的制度が充実している日本では、それらを知ることこそが「お金に困らない人生」への第一歩です。
保険を「入っているから安心」ではなく、「必要な場合は、最低限だけ入る」という考え方に切り替えていきましょう。
ご質問やご感想があれば、ぜひコメントやメッセージでお寄せください。
それではまた次回お会いしましょう。