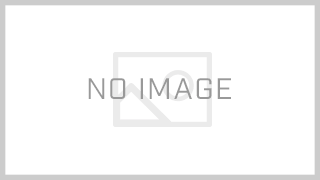亡くなった人の口座はいつ凍結される?知らないと損する相続と預金の正しい手続き
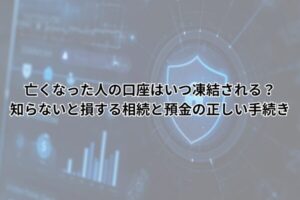
亡くなった人の口座はいつ凍結される?知らないと損する相続と預金の正しい手続き
はじめに
身近に起こり得る「相続」の話ですが、多くの方が詳しい手続きや仕組みを知らないまま、いざという時に慌ててしまいます。
今回は「死亡届を出したら口座はすぐ凍結されるのか?」を中心に、元金融機関勤務の立場から分かりやすく解説していきます。
このチャンネル・ブログでは、金融機関や周りの人が教えてくれないお金の知識を、
40歳でリタイアした私「鼻つぶれぱぐ男」が発信しています。
一人でも多くの方が、お金に振り回されない人生を送れるようなお話をお届けします。
参考記事
https://limo.media/articles/-/77783
(出典:くらしとお金の経済メディア)
■ 亡くなった人の口座は「死亡届を出したら即凍結」ではない
最初に大きな誤解からお伝えします。
死亡届を役所に提出しただけでは、銀行口座は凍結されません。
死亡情報は、市役所 → 他市町村へは共有されますが、銀行へ自動で通知される仕組みはありません。
では、いつ凍結されるのかというと、
家族が銀行へ「亡くなりました」と伝えた瞬間です。
つまり、銀行に知らせない限り、口座はそのまま使える状態ということになります。
ちなみに銀行間も連携していませんので、亡くなったと伝えた金融機関の口座だけ凍結されます。
■ 銀行員が気付いた場合は?
新聞に訃報が載る時代には、銀行員が自主的に凍結することもありましたが、現在はほとんどありません。
ただし、地域が小さく、顔が知られている場合などは、銀行員が気づけば凍結されることもあります。
■ 口座が凍結されるとどうなるのか?
凍結されると、以下の動きになります。
| 内容 | 結果 |
|---|---|
| ATM・窓口での入出金 | 不可(但し、葬式代などは一部出せる場合あり) |
| 年金 | 振込不可(年金事務所で手続き必要) |
| 電気・ガス・水道などの自動引落 | すべてストップ |
特に 公共料金の引落が止まる のは、意外と見落とされがちです。
相続手続きが終わるまで、振込用紙が届き、現金払いに勝手に切り替わります。
■ 亡くなる前に家族が勝手にお金を引き出していいのか?
暗証番号が分かるからといって、勝手に引き出すと トラブルの原因になります。
後から「使い込みだ」と言われてしまうケースは非常に多いです。
どうしても必要な支出がある場合は、
- 何のために使ったのか
- いくら使ったのか
- 領収書・メモを必ず残す
- 事前に相続人全員に相談してから、出す。
これが鉄則です。
家族仲が良くても、相続では揉めることがあります。
「お金は縁の切れ目」という言葉は、本当にその通りです。
嫌な言い方ですが、「自分の家は仲がいいから、関係ないと思っているあなた」
相続人の現状はその時で変わります。
「お金に困っている」
「結婚して、パートナーができた」
誰も将来はわかりません。
■ 預金の「払い戻し制度」を活用する
相続手続きが完了する前でも、葬儀費用など必要な資金を 一定額だけ引き出せる制度 があります。
金額は金融機関や預金額により異なります。
相続が始まってから慌てないためにも、制度の存在は知っておきたいところです。
■ 事前にできる「争族」対策
最も大切なのは、次の2点です。
- 親と生前に話しておくこと
- 資産を整理しておくこと(口座やカードを減らすなど)
言いにくいテーマですが、話しておくと手続きが圧倒的にスムーズになります。
■ まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 死亡届を出しても口座は即凍結されない | 銀行へ知らせた時点で凍結 |
| 凍結後はすべての引き落としが止まる | 生活費・葬儀費で困るケース多い |
| お金を引き出す場合は証拠を残す | 揉める原因になるため要注意 |
| 生前に家族で話すことが最重要 | 争族を未然に防ぐ |
相続は「知っているか知らないか」で大きく結果が変わります。
ぜひ今日の話を、家族との会話のきっかけにしてみてください。