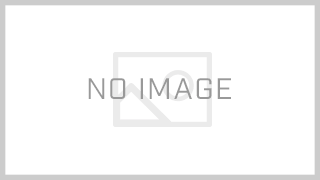AIバブルの行方と次の主役はどこか?ドットコム時代から学ぶ長期投資のヒント
AIバブルの行方と次の主役はどこか?ドットコム時代から学ぶ長期投資のヒント
はじめに:AIバブル相場の今をどう見るか
皆さんこんにちは。鼻つぶれぱぐ男です。
このブログでは「金融機関や周りの人が教えてくれないお金の話」を、40歳でリタイアした私の視点から発信しています。
今回は、**「もし今がAIバブルだとしたら、次に来るトレンドはどこなのか?」**というテーマで考えていきます。
最近は「AI関連銘柄が上がっている」「データセンター関連が強い」といったニュースをよく耳にします。
しかし、このような相場は過去にも何度もありました。
1990年代のドットコムバブルのように、熱狂の裏には必ず冷却期が訪れるのが市場の常です。
ドットコムバブルに学ぶ「設備投資の罠」
ドットコムバブルの時代、多くの企業が「インターネットの未来」に賭けて巨額の資金を投入しました。
その中心にあったのが光ファイバー網への過剰投資です。
通信インフラが未来を変えると信じられていましたが、結果として多くの設備は使われないまま「ダークファイバー」として放置されました。
しかし、その後の展開が重要です。
この使われなかった光ファイバーを安く買い取り、活用したのがGoogleやYouTubeのような企業でした。
彼らはインフラを再利用することで、世界を変えるサービスを築き上げたのです。
つまり、バブルの崩壊こそが次の成長企業を生む土壌になったとも言えます。
現代の「光ファイバー」はデータセンターか
では、今のAIバブルで同じ構図を考えるとどうでしょうか。
現在の「光ファイバー」にあたるのは、まさにデータセンターだと思います。
AIの需要増に対応するため、世界中の大手テック企業が巨額の資金を投じてデータセンターを建設しています。
これはインフラ投資そのものであり、将来のAI需要が想定通りに伸びなければ、「ダークデータセンター」と化すリスクもあります。
しかし、長期的に見ればこの過剰投資が次の主役企業の誕生につながる可能性があります。
AIが社会基盤となる未来を見据えて、今の投資をどう捉えるかがポイントです。
投資の基本は「バイ・アンド・ホールド」
ここで焦って個別銘柄を追いかける必要はありません。
資産形成の軸が低コストのインデックスファンドであれば、長期的にはトレンドに自然と連動していきます。
例えば、S&P500や全世界株式(オールカントリー)は常に時代の強い企業が入れ替わりながら組み込まれます。
つまり、個人がトレンドを完璧に読まなくても、インデックスを持ち続けることで長期的な成長を取り込める仕組みなのです。
資金の流れを読む:アメリカから世界へ
アメリカ株が長らく市場を牽引してきましたが、資金が一国に集中しすぎると、やがて他国へも流れていきます。
ドルが弱くなる局面では、相対的に欧州や新興国、金などへの資金流入が起きることもあります。
ここで重要なのは、「アメリカ株が下がった=終わり」ではないという点です。
資金の流れは循環しており、アメリカから出たお金が他国の株価を押し上げる場合もあります。
市場全体を俯瞰し、冷静に資本の動きを見る視点が欠かせません。
次のトレンド候補:ステーブルコインとデジタル決済
AIだけでなく、ステーブルコインやブロックチェーン技術を活用したデジタル決済も、次の長期トレンドになり得ます。
各国でデジタル通貨の実用化が進めば、既存の決済インフラ(Visa・Mastercardなど)に影響を与える可能性があります。
ここでも「AI+金融インフラ」という新しい融合が見られるかもしれません。
もしこの分野で新しいプラットフォームを築く企業が現れれば、次のGoogleやYouTubeになるかもしれません。
サテライト投資で未来に備える
私はコア資産としてインデックスファンドを保有しつつ、サテライト投資で新しい分野に少額投資をしていこうと考えています。
推奨ではありません。
このように、基盤を守りつつトレンドを少しだけ追うスタイルは、リスクを抑えながら未来への可能性を取り込む方法です。
「当たるか外れるか」は誰にも分かりません。
しかし、時代の流れや過去の事例を踏まえて考える習慣を持つことが、長期投資では何より大切だと思います。
まとめ:バブルを恐れず、流れを読む
AIバブルが本物なのか、それとも過熱なのか。
答えは誰にも分かりません。
ですが、ドットコム時代の教訓を思い出すことで、見えてくるものがあります。
いつかはわかりませんが、バブルの崩壊は終わりではなく、新たなスタートの合図でもあります。
重要なのは、流れを読み、慌てず、淡々と自分の投資軸を守ることです。
AIも市場も常に変化しています。
「次の主役は誰か?」を考えながら、長期的な目線で資産を育てていきましょう。
今日も一緒に、お金の未来について考えていただきありがとうございました。