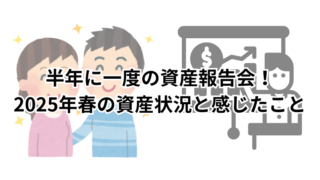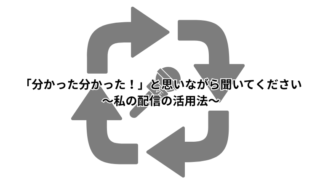ETFと投資信託の違いとは?20年後の資産形成に差が出る“分配金の扱い”
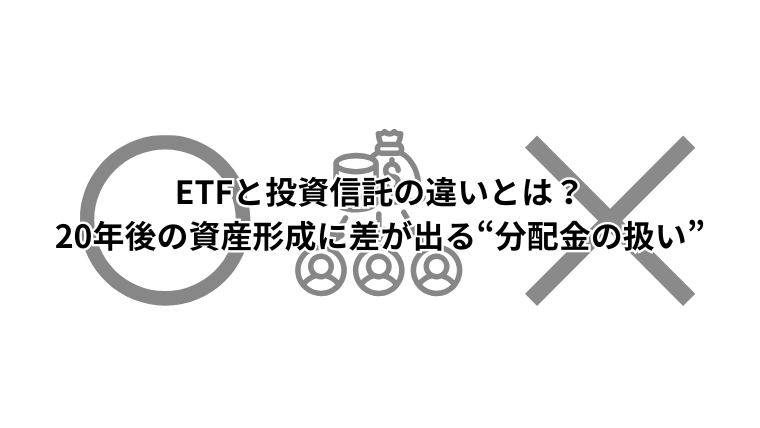
ETFと投資信託の違いとは?20年後の資産形成に差が出る“分配金の扱い”

金融機関が教えてくれないお金の話を今日もお届けします
皆さん、おはようございます。
40歳でリタイアした鼻つぶれぱぐ男です。
このブログでは、金融機関や周りの人がなかなか教えてくれない「身近なお金の話」を配信しています。
一人でも多くの方が「お金に困らない人生」を送れるように、私自身の経験をもとに発信しています。
本日は、リスナーさんからいただいたご質問にお答えする「質問回答コーナー」です。
質問内容:ETFと投資信託、20年後のリターンに違いはある?
リスナーさんからいただいた質問は以下のとおりです。
「まとまった金額を米国ETFか投資信託、どちらかに一括投資する予定です。
手数料や税制などの条件をすべて同じとしたうえで、20年間保有し、その後一括で売却するとした場合、両者のリターンに違いはありますか?
受け取りはドルか円かの違いだけと考えていいでしょうか?」
ご質問ありがとうございます!
Amazonミュージックでの音声配信を半年以上聴いてくださっているとのことで、とても嬉しく思います。
結論:最大の違いは「分配金の扱い」にあります
ご質問の前提として、手数料・税制・信託報酬などがすべて同条件ということですが、リターンに影響を与える「決定的な違い」が一つあります。
それは、分配金(配当金)が出るかどうかです。
投資信託の特徴
投資信託(例:eMAXIS Slim S&P500など)は、分配金を自動的に再投資してくれる仕組みです。
つまり、配当金が出ることなく、ファンドの中で複利運用され、雪だるま式に資産が増えていきます。
→ 20年後に一括で受け取る戦略であれば、投資信託が有利です。
米国ETFの特徴
一方、米国ETF(例:VOOなど)は、年に4回分配金(配当金)が支払われるのが基本です。
その都度、自分で再投資することも可能ですが、NISAなど非課税枠を使っている場合、その枠を消費してしまう可能性があります。
→ 分配金を「自分で使いたい」人や、再投資先を選びたい人にはETFが向いています。
長期保有による分配金の“成長”もETFの魅力
ETFを長期保有すると、企業の増配によって配当金も増えていく可能性があります。
たとえばVOOの現在の配当利回りは約1.5%ですが、20年後には3〜5%の配当利回りになっている可能性も。
このように、ETFは将来の私的年金的な使い方もできます。
投資信託が向いている人
- 現在の生活に余裕があり、分配金を使う必要がない
- 20年後にまとまった金額を一括で使いたい
- 自動で複利運用してくれる仕組みが理想的
米国ETFが向いている人
- 配当金を途中で受け取り、生活費やお小遣いに使いたい
- 再投資先を自由に選びたい
- 20年後に「分配金で生活したい」と考えている
まとめ:選択はライフスタイルと目的次第
ETFと投資信託は、どちらも素晴らしい商品です。
しかし、**「分配金が出るかどうか」**という点が、長期保有における最大の違いになります。
私のように完全リタイアをしている方や、セミリタイアして副収入を得ている方であれば、今の段階からETFの分配金を使いながら、将来はその増配を年金代わりに使うという選択肢もあります。
一方で、現在仕事をしており資金に余裕がある方は、投資信託で20年間しっかりと複利運用するのも堅実な戦略です。
ご質問はいつでも大歓迎です!
今後も、皆さんからの質問を音声配信やブログで取り上げていきます。
コメント欄でもレター機能でも構いませんので、どんな内容でもお気軽にお寄せください。
お金の話はもちろん、セミリタイア生活についてもお答えしていきます。
ということで、今日も気をつけていってらっしゃい!