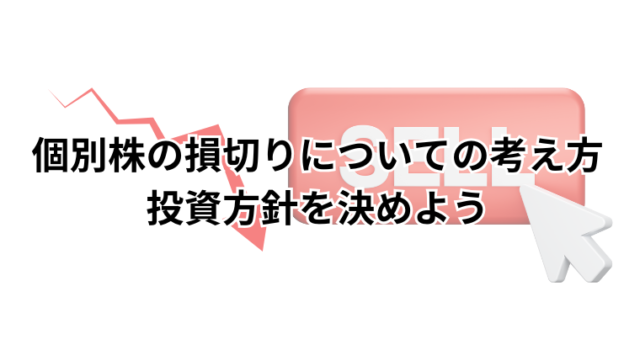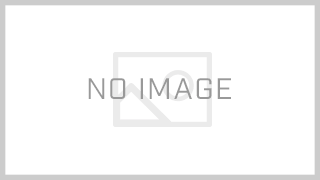不動産クラウドファンディングは危険?トラブル事例から学ぶ投資リスクと安全な代替手段
不動産クラウドファンディングは危険?トラブル事例から学ぶ投資リスクと安全な代替手段
はじめに
このチャンネルでは、金融機関や周りの人があまり教えてくれない「身近なお金の話」をお伝えしています。
40歳でリタイアした私が、実体験や最新ニュースをもとに「お金に困らない人生」を目指すためのヒントを発信しています。
本日は「何度でも言いますシリーズ」と題して、不動産クラウドファンディング(以下、不動産クラファン)について取り上げます。
結論から申し上げますと、不動産クラファンはやめたほうがいいです。
不動産クラウドファンディングとは?
不動産クラファンとは、投資家から資金を集め、事業者が不動産を取得・運用し、家賃収入や売却益を配当として投資家に分配する仕組みです。
少額から不動産投資ができる点や、7~10%といった高利回りの案件が多いことから人気を集めています。
しかし、その裏では大きなリスクが潜んでいるのです。
最近多発している不動産クラファンのトラブル事例
1. ヤマワケステートの償還遅延
札幌市の集合住宅を対象としたファンドで、本来は2025年2~5月に投資家へ資金を返還予定でしたが延期されています。つまり「返すはずだったお金を返せない」状況になっており、今後は元本が全額戻るのか不透明な状態です。
2. ダイムラコーポレーションの破産
沖縄県の物件を対象にしたファンドを運用していた事業者が、2024年7月に破産手続きを開始しました。約380人の投資家が資金を投じており、投資資金が戻らない可能性が極めて高い事例です。
3. みんなで大家さんの分配遅延
「誰でも大家になれる」と宣伝されていた有名サービスですが、2024年7月末支払予定の分配金が遅延しました。累計2000億円以上の資金を集めていることから、もし破綻すれば投資家への影響は甚大です。
なぜ不動産クラファンは危険なのか?
- 情報開示の不透明さ
株式やJリートに比べて、不動産クラファンは法的規制や情報開示が緩く、投資家がリスクを正しく把握しにくい状況にあります。 - 事業者リスクが高い
投資対象の不動産ではなく、運営会社そのものが破綻するケースもあります。事業者破綻=投資資金が消えるというリスクが現実化しています。 - 高利回りに潜む罠
7~10%の高利回りは魅力的に見えますが、裏を返せば「それだけリスクが高い」ということです。
安全な代替手段:Jリートやインデックス投資
「どうしても不動産に投資したい」という方には、不動産クラファンではなく Jリート(日本版不動産投資信託) をおすすめします。
- 東証に上場しており、株式と同じように売買が可能
- 不動産を複数組み合わせた分散投資が可能
- 情報開示も厳格で、透明性が高い
さらに、不動産に限らず 株式インデックスファンドやETF、日本国債といった王道の投資手段の方が、リスクを抑えつつ長期的に安定した運用が可能です。
投資で大切なこと
有名人やインフルエンサーが宣伝しているからといって、その投資が安全とは限りません。広告や口コミに流されず、自分自身でリスクを理解し判断することが最も重要です。
私自身も暗号資産やNFTなど未成熟な分野に投資していますが、最悪ゼロになってもいい範囲でしか資金を投入していません。
資産の大部分は、インデックス投資や国債といった王道の資産に分散しています。
まとめ
不動産クラウドファンディングは「少額で始められる」「高利回り」といった魅力がありますが、実際には 償還遅延・分配遅延・事業者破綻 といった深刻なトラブルが相次いでいます。
これから資産形成を考える方には、まずは Jリートやインデックス投資 といった透明性の高い商品を選ぶことを強くおすすめします。
投資は「一攫千金」ではなく「長期的に資産を守り育てるもの」です。
流行に流されず、王道の投資で堅実に資産を築いていきましょう。
👉 このブログでは、金融機関が教えてくれない「本当に役立つお金の話」を発信しています。
ぜひ参考にしていただき、安心して資産形成を進めてください。