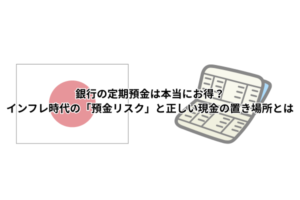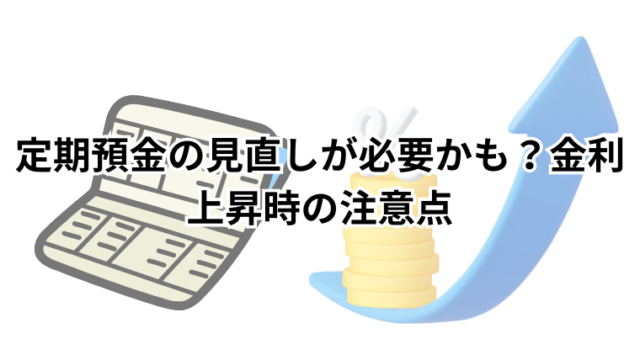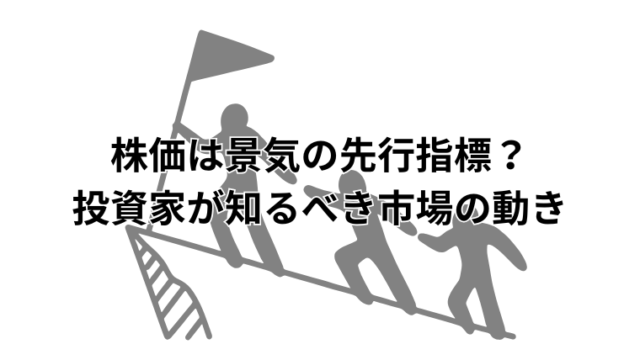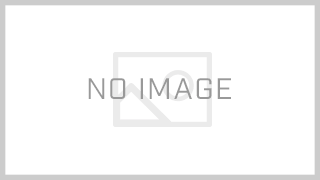銀行の定期預金は本当にお得?―インフレ時代の「預金リスク」と正しい現金の置き場所とは
銀行の定期預金は本当にお得?―インフレ時代の「預金リスク」と正しい現金の置き場所とは
はじめに:預金の常識が変わる時代です
こんにちは、鼻つぶれぱぐ男です。
このブログでは「金融機関や周りの人が教えてくれないお金の話」を、40歳でリタイアした私の実体験をもとにお届けしています。
今回は、standFMでいただいた質問「銀行の定期預金はどこがいいのか?」というテーマについて解説します。
特に、楽天銀行やゆうちょ銀行などの金利、そして「インフレが進む今、預金にどんなリスクがあるのか」まで深掘りしていきます。
銀行の金利は「どこもほぼ同じ」
まず結論から言うと、「今使っている銀行で十分」です。
なぜなら、銀行間の金利差はほとんどなく、定期預金を乗り換えても大きなリターンの差は出にくいからです。
たとえば、一般的な銀行の普通預金金利は 0.2%程度。
定期預金でも、1年ものでは 0.3%前後 が平均的です。
つまり、100万円を預けても年間でわずか数千円程度しか増えません。
一見「安全」に思える預金ですが、インフレが進行している今、実質的には資産が目減りしている可能性があります。
楽天銀行の「マネーブリッジ」で金利を上げる方法
質問でもあった「楽天銀行」は、金利面ではやや優秀です。
特に楽天証券と連携できる「マネーブリッジ」というサービスを利用すると、普通預金でも 年0.22~0.28%の優遇金利 が適用されます。
仕組みはシンプルで、楽天証券と楽天銀行の口座を連携させるだけです。
これにより、普通預金に300万円までなら 0.28% の金利がつき、定期預金よりも流動性の高い運用が可能になります。
つまり「使いたいときに引き出せるのに金利が高い」という点で、
マネーブリッジは非常に使い勝手の良い仕組みです。
低金利時代の「預金リスク」とは
「預金にリスクなんてあるの?」と思う方も多いでしょう。
しかし、今のように物価が上昇している状況では、インフレによる実質目減りが最大のリスクです。
たとえば、物価が年3%上昇しているのに、預金金利が0.2%しかなければ、
実質的に毎年2.8%ずつお金の価値が減っていく計算になります。
日本は長年デフレでしたが、最近は食料品や日用品、光熱費などが軒並み値上がりしています。
この「お金の価値が下がる時代」において、預金一本の資産管理は危険です。
どれくらい現金を持っておくべきか
それでも生活に必要な現金は確保する必要があります。
目安としては、以下のように考えると良いでしょう。
- 会社員の場合:生活費の半年〜1年分+突然の出費代100万〜300万円
- フリーランスの場合:生活費の1〜2年分+突然の出費代100万〜300万円
これらは「生活防衛資金」として普通預金に置き、
それ以上の余剰資金は投資に回すことで、インフレに負けない資産形成が可能になります。
投資を怖がらずに「仕組み」で増やす
多くの人が「投資=怖い」「損するかも」と思い込んでいますが、
実際には、時間を味方につけることで安定的に増やすことができます。
たとえば、 S&P500や全世界インデックスファンド。
これらは長期的に右肩上がりの成長を続けており、長期で見ればプラスになる可能性が高いです。
重要なのは「一気に大金を投資しない」こと。
毎月の積み立てでリスクを分散すれば、インフレに強く、精神的にも安定した運用ができます。
銀行破綻リスクと「ペイオフ制度」
万が一銀行が破綻しても、1,000万円までは「ペイオフ制度」で保護されます。
しかし、1,000万円を超える預金は保証されません。
また、証券口座に現金を置いておく場合も、基本的には信託保全によって守られています。
「銀行だから安全」という時代は終わり、
これからは「どこに、どのくらい置くか」を自分で考えることが求められます。
まとめ:預金も「戦略」が必要な時代へ
預金は「安全」ではありますが、「増えない」「減るリスクもある」資産です。
楽天銀行のマネーブリッジのような優遇制度を活用しつつ、
生活費の範囲を超える資金は投資で増やす工夫が大切です。
そして、何よりも重要なのは「知っているかどうか」。
情報を持っている人だけが、静かに資産を守り、増やしているのです。
鼻つぶれぱぐ男でした。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回も「お金に困らない人生」を目指すためのヒントをお届けします。