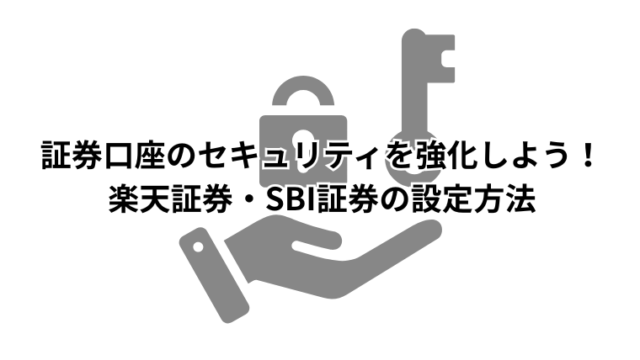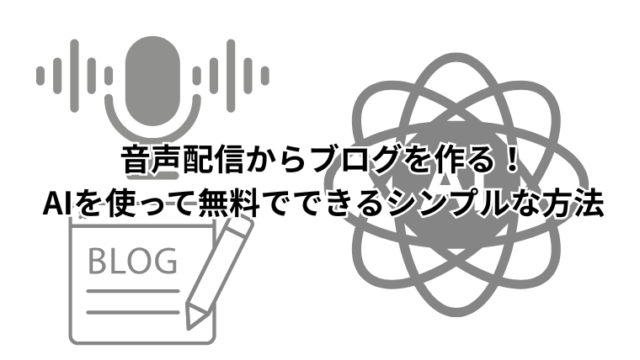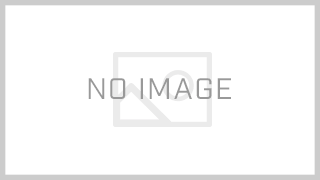就業規則と法律はどちらを優先すべき?副業・労働ルールの正しい考え方
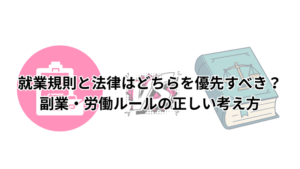
就業規則と法律はどちらを優先すべき?副業・労働ルールの正しい考え方
はじめに
みなさんこんにちは、鼻つぶれぱぐ男です。
私は40歳でリタイアし、現在はお金や働き方について発信しています。
今回は「就業規則と法律、どちらを優先すべきか?」というテーマでお話しします。
特に副業禁止規定に悩んでいる会社員の方にはぜひ知ってほしい内容です。
結論から言えば、優先されるのは法律です。
これは大前提として覚えておきましょう。
就業規則と法律の関係
会社には必ず「就業規則」があります。
勤務時間や休暇、副業に関するルールなど、社員の行動を制限するために定められているものです。
しかし、いかに詳細に定められていても、就業規則は法律に勝てません。
日本の法体系では、憲法や民法、労働契約法などが優先されます。
就業規則はあくまで会社内部のルールに過ぎず、法律に反する内容であれば無効とされるのです。
副業禁止と憲法の「職業選択の自由」
副業を例に考えてみましょう。
就業規則で「副業禁止」と書かれている場合、多くの人は「やってはいけないんだ」と思い込みます。
ですが、日本国憲法第22条には「職業選択の自由」が明記されています。
国民は自由に職業を選び、働く権利を保障されているのです。
したがって、副業そのものを一律に禁止することは、憲法の趣旨に反します。
副業をする際に注意すべき3つのポイント
では「就業規則に副業禁止とあるけど、副業して大丈夫なのか?」と心配する方へ。
バレないように行うための注意点を3つ挙げます。
- 副業を口外しない
同僚や友人に「副業をしている」と話すと、あっという間に広まります。副業は自分と家族だけの秘密にしましょう。 - 住民税を別納にする
確定申告の際に「住民税は給与から天引きではなく、普通徴収(自分で納付)」を選択してください。これで会社の給与明細から副業収入がバレるリスクを防げます。 - 市役所で確認する
毎年6月ごろに届く住民税の通知より前に4月の終わりぐらいに、市役所で直接、普通徴収か確認することも有効です。副業収入が会社経由で伝わっていないか確認できます。
この3つを守れば、副業が会社にバレる可能性は大きく下がります。
就業規則が有効になる場合とは
ただし、就業規則がまったく無効というわけではありません。
労働契約法や民法の規定に基づき、会社は業務に支障をきたさない範囲で就業規則を定めることができます。
例えば、
- 長時間労働で健康を害する
- 本業の業務に支障が出る
- 会社の秘密を利用した副業を行う
こういったケースでは、副業禁止規定が合理的と判断され、制限が有効になる場合があります。つまり、「本業に悪影響を及ぼさない」ことが大前提です。
公務員は別ルール
注意すべきは、公務員の場合です。
民間企業の社員と異なり、公務員は法律で原則副業禁止とされています。
ただし、例外的に許可を得て認められるケースもあるため、事前に申請が必要です。
泣き寝入りはNG!相談先を活用する
副業だけでなく、有給休暇や労働契約に関しても、会社の就業規則が法律に反している場合があります。
そのようなときは泣き寝入りせず、労働基準監督署や労働局に相談することが大切です。
まとめ:法律を正しく理解して働き方の選択肢を広げよう
就業規則と法律の優先関係を整理すると以下の通りです。
- 法律 > 就業規則(法律が常に優先される)
- 副業は憲法で保障された「職業選択の自由」
- 本業に支障が出る場合や、公務員は制限がある
- バレない副業には「口外しない」「住民税は別納」「市役所で確認」が重要
会社員であっても、法律を正しく理解すれば、働き方の自由度は大きく広がります。
副業に挑戦したい方は、まずは制度を理解し、安心して一歩を踏み出してください。
私自身もリタイアまでの道のりで多くの挑戦をしてきました。
みなさんも「就業規則だから無理」と思い込まず、自分の可能性を広げる行動をぜひ選んでみてください。