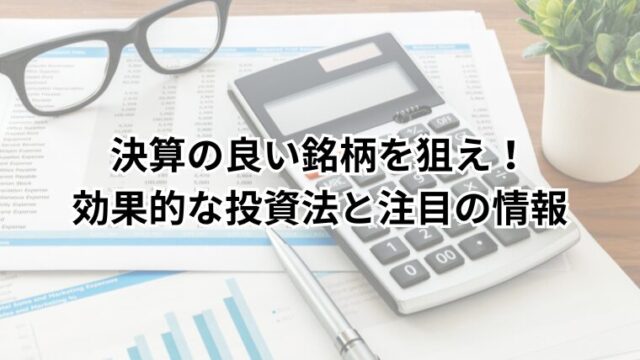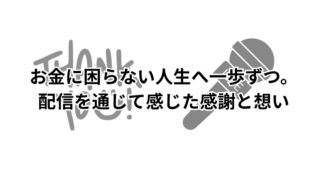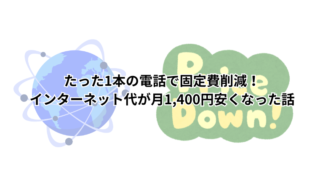高齢者向け「プラチナNISA」誕生?分配金型投資信託の危うさを解説します
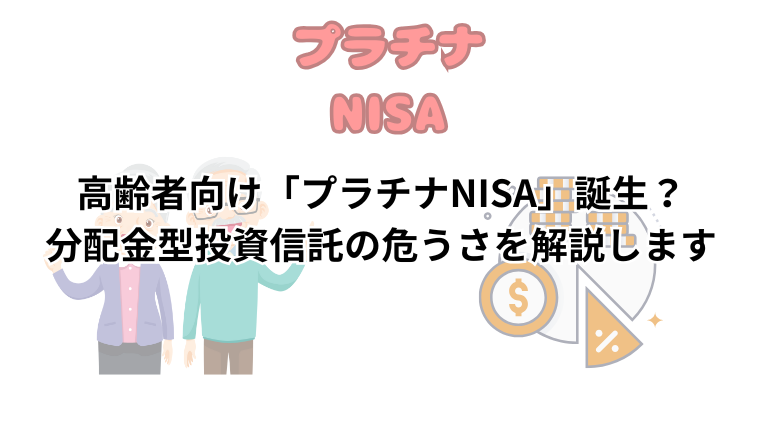
高齢者向け「プラチナNISA」誕生?分配金型投資信託の危うさを解説します

はじめに:お金の知識、届けます
みなさん、おはようございます。鼻つぶれぱぐ男です。
このチャンネルでは、金融機関や周りの人がなかなか教えてくれない「へぇ~」と思えるお金の話を発信しています。
今回のテーマは、「子どもや高齢者向けのNISA制度の拡充」についてです。
子どもNISA・高齢者向け「プラチナNISA」構想とは?
最近ニュースになっていたのでご存じの方もいるかもしれませんが、「子どもNISA」や「プラチナNISA」と呼ばれる制度が検討されています。
名前は仮称ですが、ジュニアNISAの復活や、高齢者向けに新しいNISA制度を作るという動きがあるようです。
その構想の中で気になるのが、「分配金付きの投資信託」が対象商品に含まれる可能性があるという点です。
分配金型の投資信託とは?よくある誤解とそのリスク
分配金というと「お小遣いのようにもらえてお得」と思われがちですが、実は落とし穴があります。
個別株の配当金は企業の利益から出され、株価とは別で支払われます。
一方で、分配金型の投資信託の多くは「タコ足配当」と呼ばれ、自分の資産からお金が取り崩されて分配される仕組みです。
つまり、基準価格(=投資信託の価値)がその分下がってしまいます。
さらに、投資信託には「信託報酬」という手数料が発生します。
これが無料になるのか有料になるのか、制度の詳細はまだ不明ですが、コストがかさむ点は無視できません。
金融機関の説明不足がトラブルを生む
過去にも、分配金型投資信託を勧められた高齢者が、「年金の足しになる」「お小遣い感覚で使える」といった説明を信じて購入し、後で損をしたという事例が少なくありません。
販売する金融機関側も仕組みを十分に理解しておらず、イメージだけで商品を勧めているケースも見受けられます。
これでは制度の趣旨から外れてしまいますし、トラブルの原因になります。
高齢者にNISAは本当に必要なのか?
高齢者がNISAを使ってはいけない、とは思いません。
人が何歳まで生きるかはわかりませんし、資産運用の自由ももちろんあります。
ただ、NISA制度の本来の目的は「長期の資産形成」です。
3年や5年で資産を築けるような甘い世界ではありません。
最近の相場を見てもわかるように、投資の世界は波乱に満ちた「しみどろの世界」です。
軽い気持ちで入って、よくわからない商品を掴まされたら…
最悪の結果になりかねません。
本当に必要なのは「仕組みを理解してもらう努力」
このブログを読んでくださっている皆さんが高齢者である可能性は低いかもしれませんが、ご両親が制度に興味を持つことはあると思います。
金融機関の窓口に行って、つい契約してしまうこともあるでしょう。
だからこそ、制度が始まる前に
「これは本当に必要なのか?」
「この商品はどういう仕組みなのか?」
を話し合うことが大切です。
制度によっては、一定年齢以上の高齢者が契約する際に家族の同意が必要になるケースもあります。
郵便局などでは、すでにそのような対応を取っているところもあります。
もし制度を作るなら…個人向け国債を非課税に?
僕自身は、「積立投資枠のNISA」は良い制度だと思っていますが、
「成長投資枠」については正直いらないと思っています。
高齢者向けに本当に優しい制度を作るのであれば、
個人向け国債(固定3年・5年、変動10年)を非課税にするという方法もあるのではないでしょうか?
利息も貯金より良く、比較的安心して保有できます。
まとめ:お金を守るために考えてほしいこと
「プラチナNISA」など新しい制度が検討される中で、
私たちが本当に考えるべきなのは「仕組みを理解せずに契約するリスク」です。
周囲の大切な人が、よく分からないまま制度に乗ってしまう前に、ぜひ一度立ち止まって考えてみてください。
投資は自己責任ですが、制度設計や販売姿勢にも大きな責任があります。
未来の安心のために、正しい知識を持って判断することが、今求められているのではないでしょうか。