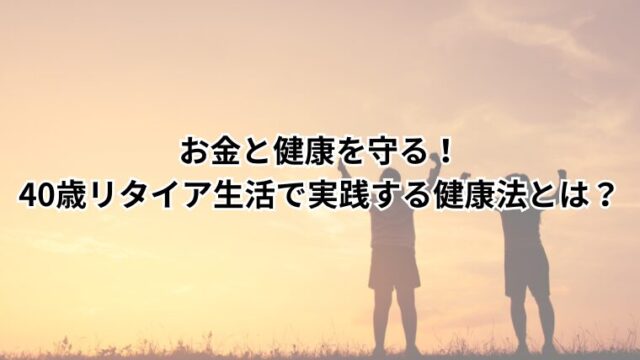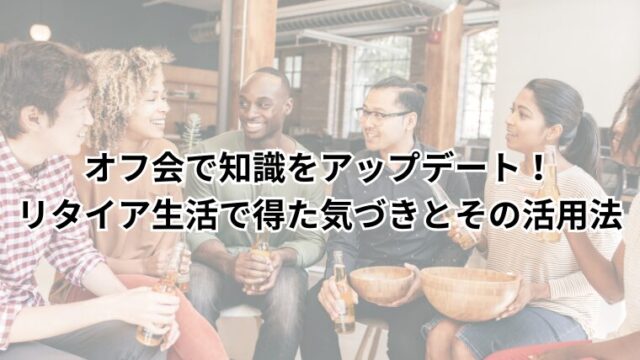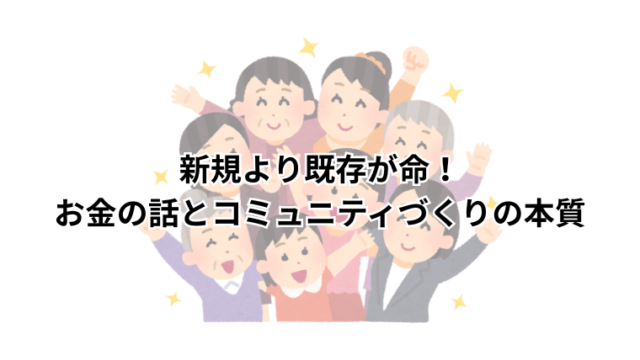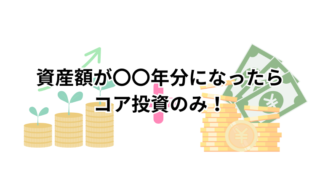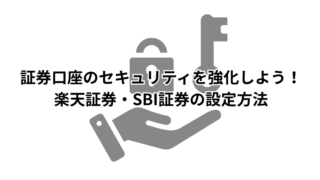青色申告の準備と心構え|個人事業主・フリーランスのための基本ガイド
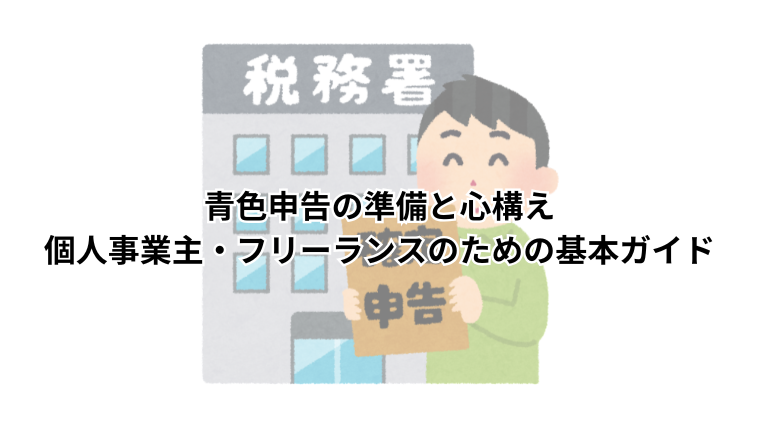
青色申告の準備と心構え|個人事業主・フリーランスのための基本ガイド

青色申告の準備と心構え|個人事業主・フリーランスのための基本ガイド
みなさん、こんにちは。鼻つぶれぱぐ男です。
今回は視聴者の方から「青色申告の準備と心構えについて教えてほしい」という質問をいただきましたので、詳しく解説していきます。
青色申告は節税メリットが大きいですが、その分しっかりとした記帳が必要になります。
これから青色申告に切り替える方、またフリーランスや個人事業主としてスタートする方に向けて、準備すべきことをお伝えします。
1. 青色申告のメリット
青色申告には、主に以下のようなメリットがあります。
- 青色申告特別控除(最大65万円の控除が可能)
- 赤字の繰越し(最大3年間繰り越せる)
- 家族への給与を経費計上(事前に届け出が必要)
白色申告よりも手間はかかりますが、節税効果が大きいため、しっかり準備して取り組む価値があります。
2. 簿記3級の勉強は必要?
青色申告をするなら、基本的な会計知識は持っておいた方が良いでしょう。
簿記3級レベルの知識があれば、日々の取引の記帳がスムーズになります。
独学でも十分ですが、通信講座を利用するのもおすすめです。
例えば、クレアールはコスパが良く、動画解説も充実しているので、基礎からしっかり学びたい方には最適です。
3. 会計ソフトの活用
手書きやエクセルでの管理も可能ですが、会計ソフトを利用することで、作業時間を大幅に短縮できます。
おすすめのクラウド会計ソフト
- マネーフォワード クラウド会計(月額料金が比較的安く、自分で記帳するスタイル)
- タックスナップ(仕分けを自動化でき、税理士監修のチェックも可能。ただし月額2,180円とやや割高)
タックスナップを利用する場合は、アプリからではなくWeb経由で登録すると安くなるので注意しましょう。
4. 経費の按分を正しく行う
フリーランスや個人事業主の場合、仕事で使用したものを経費として計上することができます。ただし、私的利用と業務利用が混在するものは「按分」が必要です。
例えば、以下のような項目は按分の対象になります。
- 自宅の家賃や光熱費(仕事で使用する時間や面積に応じて按分)
- インターネット・携帯料金(仕事で使用する割合を計算)
- パソコン・スマホの購入費用(業務利用の割合に応じて計上)
按分の割合は明確な基準がないため、自分の業務内容に応じて適切に決めましょう。
タックスナップなどのサービスを利用すると、自動で按分を算出してくれる機能もあります。
5. 青色申告の手続き方法
青色申告をするためには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出期限は事業開始から2ヶ月以内またはその年の3月15日までです。
申請方法は以下の通りです。
- 最寄りの税務署で申請書を受け取る、または国税庁のサイトからダウンロード
- 事業内容や開業日を記入し、税務署へ提出(郵送・持参・電子申請OK)
- 受理されれば、翌年の確定申告から青色申告が可能
すでに2025年が始まっている場合は、できるだけ早く税務署に相談し、手続きを進めましょう。
6. まずはやってみることが大事!
青色申告は慣れないうちは難しく感じるかもしれませんが、会計ソフトを活用すれば、そこまで大変ではありません。
また、申告時にミスをしても、税務署の指摘に従って修正すれば問題ありません。「間違ったらどうしよう」と気負わず、まずは挑戦してみることが大切です。
おすすめの参考書
- 『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!』(大河内薫 著)
これらの書籍も活用しながら、青色申告の知識を深めていきましょう。
まとめ
青色申告の準備として、以下の点を押さえておきましょう。
✅ 青色申告は節税メリットが大きい(特別控除・赤字繰越など)
✅ 簿記3級の知識があるとスムーズ(クレアールなどの通信講座もおすすめ)
✅ 会計ソフトを活用すると便利(マネーフォワード or タックスナップ)
✅ 経費の按分を適切に行う(家賃・通信費・光熱費など)
✅ 税務署で青色申告の申請を忘れずに!(早めの手続きが重要)
青色申告に挑戦することで、ビジネスの基礎を学び、資金管理能力も向上します。焦らず、一歩ずつ取り組んでいきましょう!
それでは、今日も良い一日を!