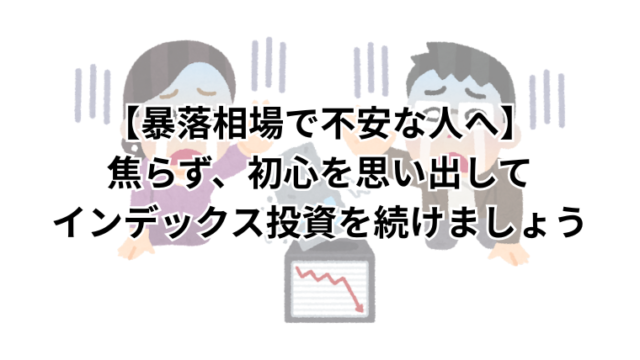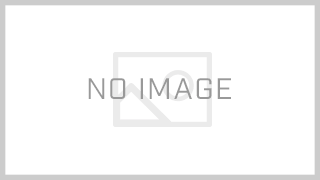10月の投資雑誌を読む:Jリート特集と「10倍株ブーム」に見る投資の落とし穴
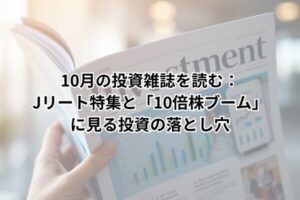
10月の投資雑誌を読む:Jリート特集と「10倍株ブーム」に見る投資の落とし穴
はじめに:投資雑誌は“逆指標”として読む
こんにちは。40歳でリタイアした「鼻つぶれぱぐ男」です。
このブログでは、金融機関や周りの人が教えてくれない“身近なお金の話”をわかりやすくお伝えしています。
今回は「10月の投資雑誌を読んで感じたこと」についてまとめます。
私は毎月2冊ほど投資雑誌をチェックしていますが、基本的には“逆指標”として見るようにしています。
雑誌が盛り上がっているテーマほど、すでに相場のピークが近いことも多いからです。
「ああ、世の中は今ここに熱気があるんだな」と客観的に眺めるようにしています。
Jリート特集の裏にあるリスク
今月の雑誌では、特に「Jリート(不動産投資信託)」が大きく特集されていました。
利回りの高さや安定性をアピールする内容が目立ちましたが、少し注意が必要だと感じます。
ここ最近、東京を中心に不動産価格が高騰しています。
ニュースやSNSでも「不動産バブル」と呼ばれるほどの盛り上がりです。
しかし、私が気になるのは“上がりすぎている”という点です。
投資の世界では「山が高ければ谷も深い」とよく言われます。
Jリートは株式市場と連動しやすく、株価が下がる局面では一緒に売られることが多いです。
特に米国株や日本株が下落相場に入ると、リートも連動して下がるケースが多く見られます。
一時的に見直されて上昇することもありますが、それは「売られすぎた反動」である場合も少なくありません。
利上げ局面が続けば、リートの期待収益は低下しやすく、結果的に価格が下がるリスクもあります。
雑誌で「おすすめ」と紹介されている時こそ、慎重に距離を取るタイミングかもしれません。
「高市相場」や「10倍株特集」への違和感
同じ号には「高市政権で動く相場」や「10倍株の見つけ方」といった特集も組まれていました。
こうしたテーマには、いかにも“短期的な期待感”が漂っています。
株式投資の世界には「期待で買って、事実で売る」という言葉があります。
つまり、政策期待や話題性で株価が上がる時期は、すでに多くの人が同じ方向を見ており、実際の成果が出る前に天井を迎えることが多いのです。
もちろん、短期トレードとして割り切って参加するなら問題ありません。
しかし、長期投資として安定した成果を狙うなら、政権やテーマよりも「企業の本質的な業績」を見るべきだと感じます。
「10倍株」は夢があるが、現実はシビア
「10倍株の見つけ方」という特集も、株高局面では必ず登場します。
ただし、冷静に見てみると“思惑先行”の印象が強いのも事実です。
今回紹介されていた銘柄をいくつか見ても、業績がしっかり伸びている企業もある一方で、すでに株価が高騰しすぎているものも多く見られました。
PER(株価収益率)が高すぎる企業は、将来の成長が織り込み済みの可能性もあります。
長期投資を前提とするなら、次のようなポイントを重視すべきだと思います。
- 売上やEPS(1株当たり利益)が着実に伸びているか
- 借入金が少なく、自己資本比率が高いか
- 営業キャッシュフローが安定しているか
- 配当金を増やしている(増配傾向)か
これらの条件を満たしていれば、急成長を狙わなくても“じわじわと伸びる株”に出会うことができます。
特集記事のような派手さはありませんが、長期的な安心感は大きいです。
投資雑誌との“ちょうどいい距離感”
投資雑誌は、相場の「空気感」を知るうえでは非常に役立ちます。
ただし、それを鵜呑みにするのではなく、“逆指標”として活用する意識が大切です。
雑誌で大きく取り上げられるということは、すでに多くの人が注目しているサインでもあります。
投資の世界では、「皆が注目しているときは出口が近い」ことも多いのです。
その意味で、雑誌を読んで「今はどこに熱があるのか」を知ることは有益です。
しかし、実際の投資判断はあくまで“自分の軸”で行うべきだと改めて感じました。
まとめ:流行よりも本質を見極める
10月の投資雑誌を読んで改めて思ったのは、「流行のテーマに飛びつかないこと」の大切さです。
Jリート特集や10倍株など、盛り上がっているテーマほどリスクも潜んでいます。
投資の本質は「長く続けられるかどうか」です。
短期的な熱狂よりも、自分が理解できる範囲で、地道に利益を積み上げていく方が結局は強い。
雑誌の情報をきっかけに、“冷静な視点”を持てる投資家が増えることを願っています。