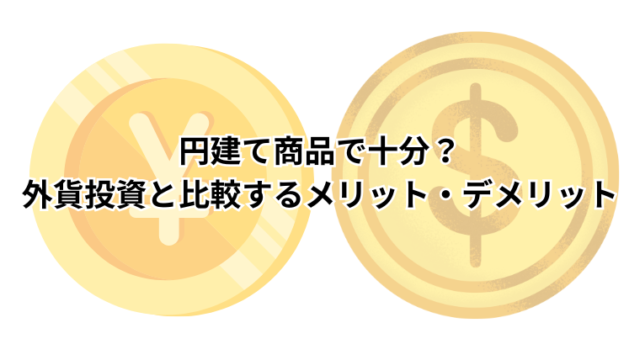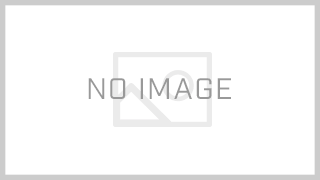金融庁が暗号資産の分離課税を要望!2026年度税制改正で何が変わるのか解説します
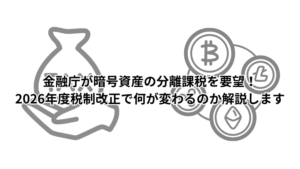
金融庁が暗号資産の分離課税を要望!2026年度税制改正で何が変わるのか解説します
はじめに
みなさん、おはようございます。鼻つぶれぱぐ男です。
このチャンネルでは「金融機関や周りの人が教えてくれない身近なお金の話」を、40歳でリタイアした私が発信しています。
一人でも多くの方がお金に困らない人生を送れるように、日々情報をお届けしています。
今回のテーマは 「金融庁が政府に暗号資産の分離課税を要望した」というニュース です。2026年度の税制改正に向け、大きな転換点となりそうな動きを整理していきます。
金融庁の税制改正要望とは
2025年8月21日付の日経新聞によると、金融庁は政府が掲げる「資産運用立国」の実現に向けて、2026年度の税制改正で以下の要望を出しました。
- NISA(少額投資非課税制度)の対象拡大
- 暗号資産の課税制度見直し(分離課税の導入)
これまで慎重だった金融庁が、自ら分離課税を要望するのは極めて異例です。
詳しくはこちらの資料を参照
(出典:金融庁)
暗号資産課税の現状と問題点
現行制度では、暗号資産の利益は「総合課税」に分類され、最大55%の高い税率が適用されます。
これにより、多くの投資家が国内での暗号資産投資に二の足を踏んでいました。
一方で株式や投資信託などは「申告分離課税」が適用され、税率は一律20%。
この差が投資の公平性を欠いていたのです。
分離課税が導入されるとどうなる?
もし暗号資産にも分離課税が導入されれば、次のようなメリットが期待されます。
- 税率が最大55%から20%に軽減
- 投資家が国内取引所を利用しやすくなる
- 海外流出していた投資資金が戻る可能性
- ビットコインETFなどの金融商品が組成されやすくなる
結果として、暗号資産市場の健全な成長が後押しされるでしょう。
投資家にとっての実践的なポイント
ここで大事なのは、制度改正の動きを「自分ごと」として考えることです。
- 投資は余裕資金で行う(ゼロになっても生活に困らない範囲)
- ビットコインや主要銘柄を中心に検討する
- レバレッジ取引は避ける
- 小額でも持つことで市場動向にアンテナを張れる
暗号資産に興味がなくても、少額保有することでニュースの見方が変わります。
これは投資だけでなく「時代の流れを知る」ことにもつながります。
日本の動きと世界の潮流
米国や欧州では、すでに暗号資産ETFや規制整備が進んでいます。
日本も遅れながらも、金融庁が方針転換を見せたことで国際的な流れに追随しつつあります。
さらに、日本ではステーブルコイン「JPYC」が承認されるなど、デジタル決済や暗号資産の環境整備が加速しています。
これも「資産運用立国」に向けた一歩です。
長期投資の視点でどう考える?
私自身は、数年前に1ビットコインを100〜150万円の水準で購入しました。
当時は「ゼロになっても構わない」という気持ちでしたが、結果的に長期保有が功を奏しています。
分離課税が実現すれば、今後も暗号資産を「長期的な資産の一部」として保有しやすくなるでしょう。
生活費の一部を補う形で少しずつ取り崩していく予定です。
注意点とリスク管理
暗号資産は値動きが激しく、リスクの高い資産です。
以下の点には特に注意してください。
- 怪しいコインや根拠のないプロジェクトには投資しない
- 借金してまで投資しない
- 長期視点を持ち、短期的な値動きに振り回されない
結局のところ「ゼロになってもいい額」で投資することが最善のリスク管理です。
まとめ
金融庁が暗号資産の分離課税を政府に要望したことは、日本の投資環境にとって大きな転換点です。
- NISA拡充と合わせて「資産運用立国」に向けた動きが進んでいる
- 暗号資産も分離課税になれば投資のハードルが下がる
- 小額からでも参加することで時代の変化を実感できる
投資は自己責任ですが、知識を持ちアンテナを張ることが何より重要です。
これからも変化の流れを一緒に追いかけていきましょう。
👉 今日も無理のない投資で、安心して資産形成を進めてください。いってらっしゃい。