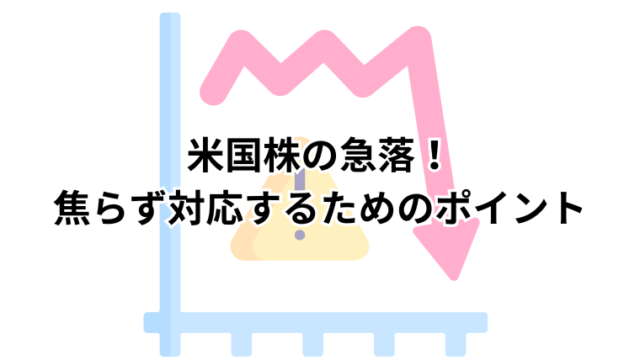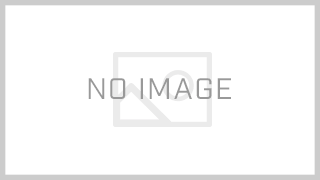西側はステーブルコイン、東側はゴールド?世界経済の分断と資産戦略を考える
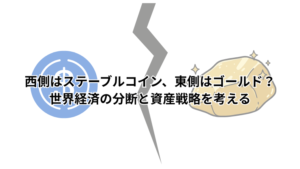
西側はステーブルコイン、東側はゴールド?世界経済の分断と資産戦略を考える
はじめに
皆さんこんにちは。40歳でリタイアし、日々お金や投資について情報発信をしている鼻つぶれパグ男です。
今回のテーマは「西側はステーブルコイン、東側はゴールド」という視点から、世界経済の動きと私たちの資産形成への影響について考えていきます。
これはあくまで私の独断と偏見を含んだ見方ですが、長期的な資産形成を考える上での参考になればと思います。
東西対立と世界経済の背景
近年、世界ではさまざまな地域紛争や代理戦争が勃発しています。
ウクライナ情勢や中東の問題などは、単なる地域の衝突ではなく、西側諸国と東側諸国の対立構造の一部でもあります。
- 西側諸国:アメリカ、日本、欧州などの先進国
- 東側諸国:中国、ロシア、中東諸国などの新興国・資源国
この構図の中で、東側は「ドル離れ」を進めています。
かつて中国は米国債を大量に保有していましたが、その比率を下げ、代わりに金(ゴールド)を積み増しています。
東側がゴールドを選ぶ理由
東側諸国は資源を豊富に持つ国が多く、レアアースや石油といったコモディティの供給を握っています。
こうした国々は、ドル依存から脱却する手段として「現物資産」である金を選んでいます。
- ゴールドは信用力が高く、長期保存が可能
- 採掘量に限界があるため、希少性が担保されている
- 東側諸国の資源戦略と親和性が高い
特に中国は「デジタル人民元」を推進していましたが、近年はその存在感が薄れ、代わりにゴールドの保有を強化しています。
これは、デジタル通貨よりも金の安定性を重視した結果ともいえます。
西側がステーブルコインを推進する理由
一方で、西側諸国はドルを基盤とした「ステーブルコイン」の普及を進めています。
ステーブルコインとは、法定通貨に連動した暗号資産で、1コイン=1ドル、1円といった形で価値が固定されます。
ビットコインのように価格変動が激しい資産とは異なり、決済手段として安定して利用できるのが特徴です。
- 日本では「JPYC」が金融庁に承認
- アメリカでは「サークル社」のステーブルコインが承認
- 決済手数料が低く、世界共通で利用可能
特に自国通貨が弱く、ハイパーインフレに苦しむ国では、安定した決済手段としてステーブルコインが歓迎される可能性があります。
西側はこうした国々にデジタル決済網を広めることで、ドルの影響力を維持・拡大しようとしているのです。
基軸通貨は変わるのか?
歴史を振り返ると、基軸通貨は時代ごとに変化してきました。
オランダのギルダー、イギリスのポンド、そして現在のアメリカドルです。
今後ドルが基軸通貨の座を失うのかどうかは誰にも断言できません。
個人的には、ドルが「一強」であり続けることはないものの、当面は強い影響力を保持し続けると考えています。
米国経済も永遠に強いわけではありませんが、基盤の信頼性や国際的な仕組みは依然として強固だからです。
投資家が意識すべきポイント
ここまでの話を整理すると、世界は「東のゴールド」「西のステーブルコイン」という二つの方向性に進んでいることが見えてきます。
投資家としては、この構造を理解したうえで以下の点を意識するとよいでしょう。
- 資産分散の重要性
株式だけでなく、金やコモディティへの分散も検討する。 - デジタル通貨の動向を注視
ステーブルコインが普及すれば、ドルの影響力が長期的に維持される可能性がある。 - 地政学リスクを意識
世界の分断が経済や市場にどう影響するかを常に考える。
まとめ
世界は「東側=ゴールド」「西側=ステーブルコイン」という構造で分断が進んでいます。東側は資源と現物資産でドル依存を脱却しようとし、西側はデジタル決済を通じてドル支配を強化しようとしています。
私たちが今すぐ何かを大きく変える必要はありませんが、この流れを知っておくだけでも投資判断の幅は広がります。
資産形成を考える際には、こうした世界の構造的な動きも頭に入れておくことをおすすめします。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
お金に困らない人生を送るために、一緒に学んでいきましょう。