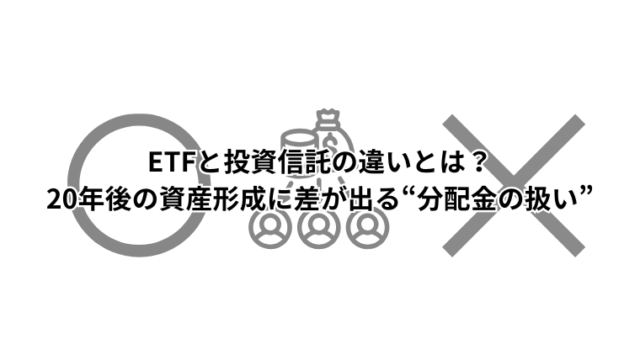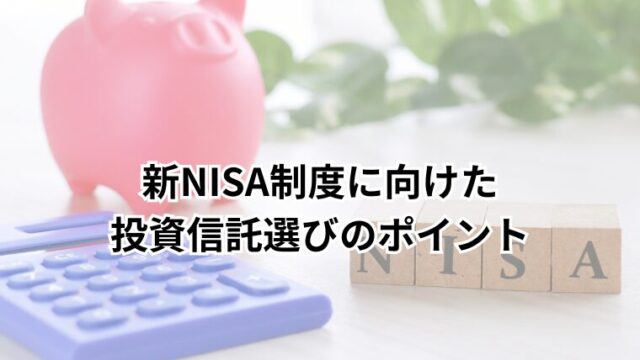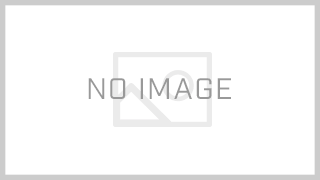知らないと損する!iDeCoの3つの落とし穴と活かし方
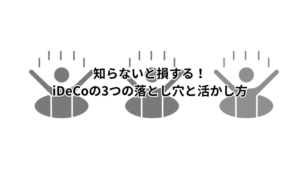
知らないと損する!iDeCoの3つの落とし穴と活かし方
はじめに
こんにちは、鼻つぶれぱぐ男です。
当チャンネルでは、金融機関や周囲がなかなか触れてくれないお金の話を、40歳でリタイアした私がわかりやすくお届けしています。
今日も、できるだけ多くの方が「お金について困らない人生」を送れるように、知っておいて損がないお金の知識を共有します。
今日は、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」について、知らないと損する3つの重要な知識を中心にお話します。
① iDeCoの基礎は知っているけれど…
iDeCoには、よく知られている3大メリットがあります:
- 掛金が所得控除になる
- 運用中の運用益が非課税
- 受取時に税制を選べる(退職所得控除/公的年金控除)
これらは金融機関やインフルエンサーが頻繁に伝えるポイントですが、これだけでは十分ではありません。
もっと深く理解して運用しないと、本当のメリットは活かしきれません。
特に、知識を自分でつけて節税や確定申告を自分で管理したい方には、さらに知っておいてほしいことがたくさんあります。
② 知られざる手数料の落とし穴──「掛け方編」
● 月払いと年払いによる手数料差
iDeCoの手数料構造には、以下が含まれます:
- 国民年金基金連合会の手数料(毎月一律105円)
- 信託銀行への手数料(毎月66円)
**月払い(最低5,000円)**で続けると、毎月171円・年換算で約3.4%のコストに相当します。
これはかなり割高です。
しかし、年払いに切り替えると「国民年金基金分105円」は1回限りになり、年間コストを約1.5%まで下げられます(月掛け5000円の場合)。
まとまった掛金を拠出できる方は、こちらの方が効率的です。
ただし、どちらを選ぶかはご自身の資金計画や運用方針によります。
● 拠出停止の注意点
掛金を拠出しない期間があると、その期間は加入年数にカウントされません。
加入年数が短くなると、退職所得控除の対象額が減るため、将来の受取時に受けられる税制優遇が減ってしまいます。
途中で休止する場合は、必ずその影響を理解しておく必要があります。
③ 運用中の切り替え──「スイッチング」の活用
スイッチングとは、既存の運用商品を別の商品に切り替えることです。
iDeCoではこの操作が非課税で可能ですが、以下の注意点があります:
- スイッチングには処理に時間がかかる場合があり、その間に利益を取り逃す可能性がある
- 処理中の値動きを見越してスイッチする判断力が必要
例えば、リスク資産から安全資産(現金や債券ファンド)に切り替えておくと、引き出し直前の暴落のリスクを避けられます。
出口戦略の一環としてスイッチングを検討することは非常に重要です。
④ 受取時の出口戦略──「出し方の手仕舞い方」
iDeCo受け取り時には、一時金として受け取る(一括)か、分割で少しずつ受け取るかを選ぶことができます。
● 一括受取(退職所得控除)
退職所得控除は**加入年数×40万円
(例:20年で800万円。20年以上からの部分は、加入年数×70万円)**と設定されています。
一時金受取ならこの控除が使えるので、税負担を抑えられる可能性が高いです。
● 分割受取(公的年金控除の適用)
分割で年金形式で受け取る場合は、公的年金等控除が適用されます。
さらに、振込ごとに約440円の手数料がかかるため、頻繁に分割するほどコストが高くなる点にも注意が必要です(年1回受け取りも可能)。
● 最適な受け取り方の見極め
受け取り方に悩む方も多いですが、暴落リスクを避けたいなら一時金受け取り前にスイッチングで現金化しておく、分割受け取りにコストや税金の抑制効果が合うならそちらを選ぶなど、ご自身のライフプランとリスク許容度に合わせて選ぶことが大切です。
⑤ まとめ:知識こそ強さ
- iDeCoの基礎メリットだけでは不十分で、知識を持つことでさらに活用できる領域があります。
- 手数料の構造を理解し、掛け方を工夫することで、コストを最小化できます。
- スイッチングや受取時の戦略を選ぶことで、税金負担や市場リスクを軽減できます。
iDeCoは一度始めれば長期運用になるため、始める前に正しい知識を持つことが重要です。投資や節税に興味がある方は、まずは基本を理解したうえで、細部まで情報を整理していくことで、お金に困らない人生へ一歩近づくことができます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
iDeCoの落とし穴や活かし方を知って、自分らしい資産形成を実践していただければ嬉しいです。
それでは、今日も気をつけていってらっしゃい!