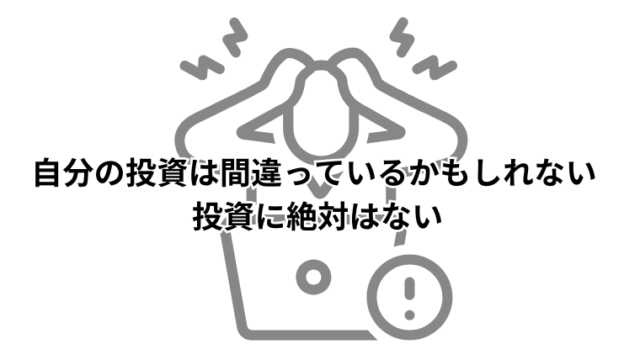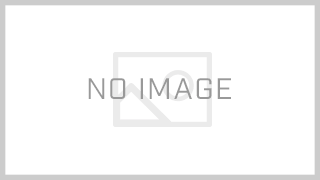確定申告の落とし穴!“配当金で損した”実体験と正しい申告のコツ
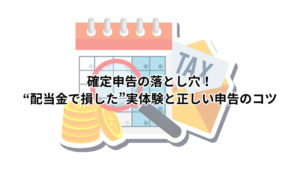
確定申告の落とし穴!“配当金で損した”実体験と正しい申告のコツ
はじめに:配信の目的とリスナーからの声
このブログでは、金融機関や周囲の人がなかなか教えてくれない、身近で「へぇ~」と思えるお金の話を、40歳でリタイアした私がわかりやすくお届けしています。
今回はリスナーの方からいただいたエピソードをもとに、「確定申告で損をしないためのポイント」をお話しします。
いただいたエピソード:2万円返ってくるはずが逆に支払い?
今回いただいたのは、こんなメッセージでした。
「3年前、持株会の配当金を申告したら、それまで2万円ほど戻ってきていたのに、逆に2万円払うことに…。4万円の精神的ダメージで、夕焼けがやけに綺麗に見えました…」
この話、他人事ではありません。
実は確定申告の内容によっては、戻ってくるはずのお金が逆に増税に変わることがあるんです。
シミュレーションは必須です!
確定申告において一番大切なのは「申告前のシミュレーション」です。
特に配当金や株の売却益を申告する際には、
入れた場合・入れない場合でどう税額が変わるか、シミュレーションしてから判断することが鉄則です。
なぜなら、申告内容によっては所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料にも影響が出るからです。
特定口座・源泉徴収ありのポイント
ほとんどの人が証券口座を「特定口座・源泉徴収あり」にしていると思います。
この場合、売却益や配当金に対する税金(20.315%)は自動で引かれます。
つまり、このような取引に関しては確定申告をしなくてもよいとされています(=「原則不要」)。
しかし、税金が戻ってくる可能性がある人はあえて申告するわけですね。
ただし、ここで注意したいのが「全部申告する必要はない」ということ。
配当金だけ載せたり、1つの口座分だけ申告することも可能です。
申告する対象は選べます
例えば2つの証券口座(AとB)で、それぞれ売却益10万円、配当金10万円、合計40万円の利益があったとします。
このとき、確定申告にはこの中の一部だけ、たとえばA口座の配当金10万円だけ申告する、という選択も可能です。
ただし、売却損がある口座で配当金控除を受ける場合はセットで申告が必要など、ルールもあります。
ここもシミュレーションが大事です。
配当金の課税区分にも注意を
配当金は「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選ぶことができます。
選び方によって、税金の戻り方も変わります。
ただし、口座ごとに課税方式を分けることはNGです。
たとえば、A口座を総合課税、B口座を分離課税といった処理はできません。
全体を統一する必要があります。
所得税だけでなく住民税・国保にも影響あり
所得税の控除枠は年々変化しており、今年は基礎控除が増えるなどの変更があります。
しかし、住民税の控除枠は変わっていないため、申告内容によって住民税が大きく上がる可能性もあります。
また、所得が上がることで国民健康保険料も連動して上がる場合があります。
これを知らずに申告して、あとから「しまった…」とならないように注意が必要です。
ふるさと納税の失敗談:寄付したのに控除されない?
ここで私自身の失敗談をお話しします。
リタイアして国保に加入していた年、楽天のふるさと納税シミュレーションで寄付上限額を計算し、実際に寄付を行いました。
ところが当時は「住民税の不要申告制度」がまだあり、株の譲渡益を住民税に反映させないよう申告していたのです。
そのため、ふるさと納税が住民税に反映されず、実質“ただの寄付”になってしまいました。
現在はその制度が撤廃されたので、確定申告書に記載したものはすべて住民税にも反映されます。
この違いはぜひ覚えておいてください。
年末に向けてやっておくべきこと
確定申告は毎年2月15日頃からスタートしますが、申告する内容は12月31日までに決まります。
ですので、年末までに以下をシミュレーションしながら準備しておくと安心です。
- 売却益・配当金の申告有無で税金がどう変わるか
- ふるさと納税の適正上限額
- 所得控除の使い方(iDeCo、小規模共済、医療費控除など)
- 住民税・国保への影響
おわりに:税金を味方にすれば未来が変わる
税金は難しく感じがちですが、正しい知識を持つことで節税や手取りアップにつながる重要なスキルになります。
確定申告前には、必ず事前にシミュレーションを行いましょう。
そして、「これは損なの?得なの?」と迷ったときには、あわてて申告せず一度立ち止まって考えることが大切です。
また、今後も皆さんからのご質問やエピソードをお待ちしています。
どんな話でも、一つの配信・一つの学びになりますので、ぜひお気軽にお寄せください。
それでは、また次回お会いしましょう。いってらっしゃい!