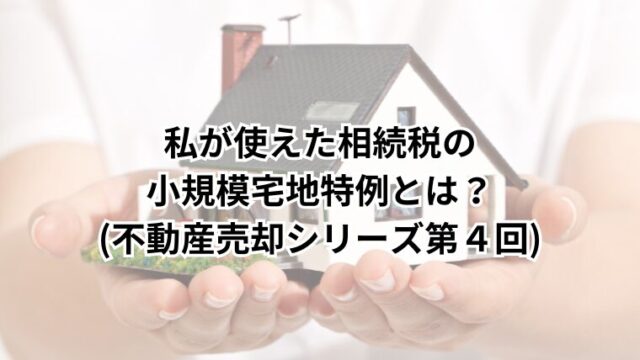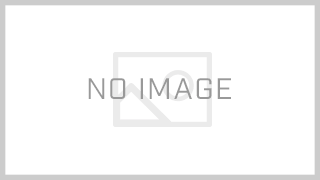妻の日本株投資を控える理由とは?扶養と税金を見据えた資産運用の工夫
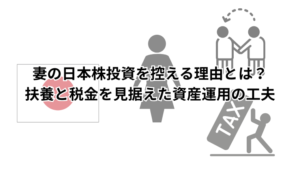
妻の日本株投資を控える理由とは?扶養と税金を見据えた資産運用の工夫
はじめに
こんにちは、鼻つぶれぱぐ男です。
このブログでは、金融機関や周囲の人があまり教えてくれない、でも「へぇ~」と思えるようなお金の話を、40歳でリタイアした私が発信しています。
今日のテーマは「妻の日本株投資を控えている理由」についてお話しします。
日本株は持っているけど…
私は配当金や将来の年金代わりになるような連続増配銘柄を中心に日本株を保有しています。
今は配当利回りが低くても、将来的に増配される可能性が高い企業に長期投資することを意識しています。
妻も同様に日本株を一部保有していますが、実はその比率はあまり高くしていません。
これは「扶養」と「税金」の問題を考慮しての判断です。
妻の資産運用はインデックス中心
妻の投資方針は、基本的に**インデックスファンドとiDeCo(個人型確定拠出年金)**を中心としています。
これは税制面で非常に有利だからです。
具体的には以下の2点を意識しています:
- 非課税枠の活用(新NISA・iDeCo)
- 扶養内に収めることでの所得税・住民税の節税
確定申告と税の取り戻し
妻の証券口座は「特定口座(源泉徴収あり)」です。
この場合、配当金や株の譲渡益に対して**20.315%**の税金が自動で引かれます。
しかし、確定申告をすることで一部の税金を取り戻すことが可能です。
たとえば:
- 所得が少なければ「基礎控除」が適用される
- 配当所得も一定条件下で「配当控除」が利用できる
- iDeCo拠出金額は、「小規模企業共済控除」も関係してくる
このように、確定申告をすることで毎年税金の還付を受けています。
扶養から外れないことが最優先
ここが一番大事なポイントです。
妻は私の扶養内であるため、所得が増えすぎると扶養から外れてしまいます。
扶養から外れると、以下のデメリットがあります:
- 私の配偶者控除や配偶者特別控除が使えなくなる
- 妻自身が住民税や国民健康保険などを払うことになる
- 世帯全体としての実質的な手取りが減る
このリスクを避けるために、妻名義ではあえて高配当株をあまり持たないようにしています。
新NISAとiDeCoは強力な味方
妻の資産運用では、新NISA(特につみたて投資枠)とiDeCoを最大限活用しています。
どちらも非課税で運用できる制度のため、配当金や売却益に税金がかからず、扶養の枠にも影響を与えにくいのです。
非課税枠が埋まってからは、やむを得ず特定口座で運用することになりますが、基本的には可能な限り非課税口座を活用する方針です。
将来の増配リスクにも注意
今は配当金が少額でも、連続増配銘柄を保有していると、将来的に配当金が増える可能性があります。
これは私の投資戦略としては歓迎すべきことですが、扶養されている妻にとっては注意が必要です。
将来、配当が大きくなりすぎると所得が扶養枠を超えてしまうかもしれません。
だからこそ、「今」の利回りだけでなく、「将来」の配当と税制も見据えて資産配分を考えることが大切です。
まとめ
妻の日本株投資を控えめにしている理由は、「扶養から外さないため」「税金を最適化するため」という2点です。
夫婦で投資をする際は、それぞれの収入や控除枠、非課税制度などをうまく活用して、トータルで最適な家計管理を目指すことが大切です。
皆さんも、パートナーが扶養内であれば、安易に配当株を買いすぎずに、将来の税制や家計への影響を考えて投資を進めてみてください。
それでは、今日も良い一日をお過ごしください。気をつけていってらっしゃい!