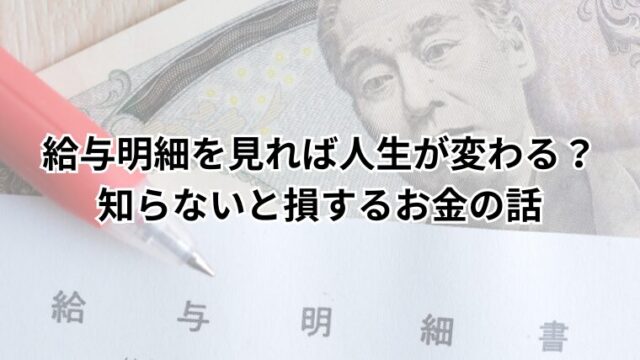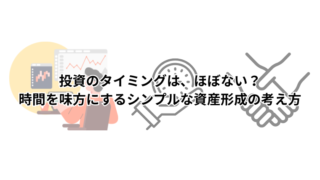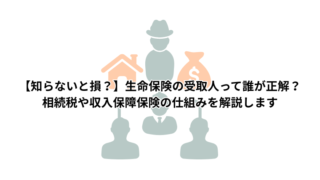教育資金は積立だけで大丈夫?40歳リタイアした私が考えるお金の賢い預け方
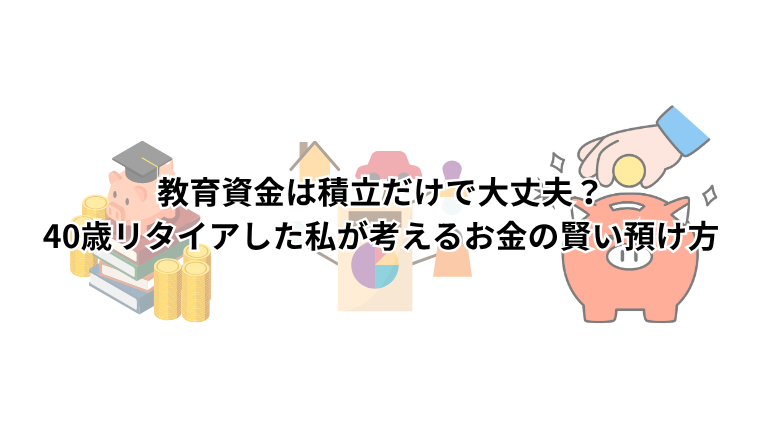
教育資金は積立だけで大丈夫?40歳リタイアした私が考えるお金の賢い預け方

はじめに
おはようございます。鼻つぶれぱぐ男です。
このブログでは、金融機関や身近な人がなかなか教えてくれない「へぇ~」と思えるお金の話を、40歳でリタイアした私が配信しています。
今回も質問をいただきましたので、お答えしていきます。
質問の内容は「お子さんの教育資金について」です。
皆さんの質問にお応えする際には、可能な範囲で情報を伏せつつ、共有可能な部分は丁寧に解説していきたいと思います。
配信を通して、一人でも多くの方が「お金に困らない人生」を送れるように応援しています。
今回のご質問:お子さんの教育資金について
ご質問をくださった方は、中学2年生と小学5年生のお子さんをお持ちで、大学進学に向けた教育資金を銀行で積み立てていらっしゃるそうです。
ボーナス時にも追加で積み立てをされているとのことですが、銀行名と金額は非公開とさせていただきます。
この方はSpotifyで私の配信をお聴きくださっていて、最近つみたて投資を始めたとのこと。
医療保険の見直しもされたそうで、とても素晴らしい一歩を踏み出されています。
教育資金に銀行積立は正解か?
銀行での積立は、安全性が高く、元本割れの心配もありません。
特に教育資金は必要な時期が決まっているため、リスクを取りにくい目的ではあります。
ただし、注意すべき点もあります。
それは「積立時の金利」です。
多くの場合、積立定期預金などは最初に契約した時の金利がそのまま適用されます。
もし低金利時代に始めていた場合、今後金利が上がっても恩恵を受けられない可能性があります。
今こそ見直したい定期預金や積立の内容
現在、日本の金利はゆるやかに上昇しています。
特に郵便局などで利用されている「定額貯金」は、金利固定のまま10年運用されるため、金利上昇局面ではやや不利です。
私も最近、過去に預けっぱなしにしていた定額貯金を見直し、1年定期に切り替えてきました。
今後は毎年の金利変更を反映できるようにしています。
もし同様の商品をお持ちの方がいれば、一度確認してみることをおすすめします。
今後の資金運用の選択肢
質問者さんのように、ある程度の教育資金を既に積み立てている方は、「これからの追加分」をどうするかがポイントです。
私は、教育資金とか貯蓄など家全体の貯蓄額で考えていくことがシンプルでわかりやすいと思っています。
その上で2つの選択肢があります。
①インデックスファンドへの積立(新NISA活用)
- すでに教育資金がある程度ある場合
- 投資のリスクを取ってもよいと感じている方
全世界株式(例:eMAXIS Slimオールカントリー)など、分散が効いた商品を活用して、長期的なリターンを目指すのも一案です。
S&P500よりも世界全体に分散された商品が無難です。
②預金を活用したシンプルな積立
- 教育資金がまだ十分でない場合
- 投資が不安な方
従来通りの定期預金や積立定期など、確実に貯まる方法で毎月積み立てていく形でも全く問題ありません。
特にお子さんの大学進学までの期間が短くなっている場合、元本保証を優先した方がよいケースもあります。
大学費用はどれくらい必要?
大学にかかる費用は、種類によって大きく異なります(※2024年現在の目安です)。
- 国公立大学(4年間):約243万円
- 私立文系(4年間):約390万円
- 私立理系(4年間):約520万円
- 私立医学部(4年間):約2,300万円
上のお子さんが大学卒業する頃に、下のお子さんが大学入学という流れになる可能性が高いため、大学費用が連続して発生する期間の資金計画も重要です。
教育資金だけじゃない!生活防衛資金の確保も重要
投資や積立を考える際、忘れてはいけないのが「生活防衛資金」です。
会社員の方であれば、最低でも半年分、できれば1年分の生活費を現金で確保しておくことをおすすめします。
万が一の病気や失業時に、生活を支える大切なお金です。
また、死亡保険や遺族年金など、いざという時の保障制度も把握しておきましょう。マイナンバーカードがあれば「ねんきんネット」などで将来の年金額や遺族年金も確認できます。
まとめ:今後の預け先はどうする?
これまでの積立はそのままでも問題ありません。
ただし、今後の追加分については、
- 金利上昇を見込んだ定期の見直し
- 新NISAによる長期投資
- 教育資金と生活費のバランス
といった点を踏まえて、トータルでの資金計画を考えることが大切です。
また、政府が「子どもNISA」のような制度を導入する可能性もあるため、その動きにも注目しておくとよいでしょう。
おわりに
お金の話は人それぞれの状況によって最適解が違います。
今回のような教育資金や生活防衛資金のバランスは、まさにその好例です。
もし自分に合った方法を知りたい方がいれば、引き続き配信やブログをご覧いただければと思います。
本日もお読みいただきありがとうございました!